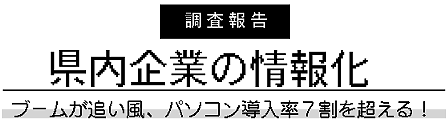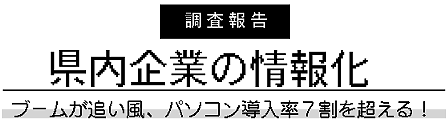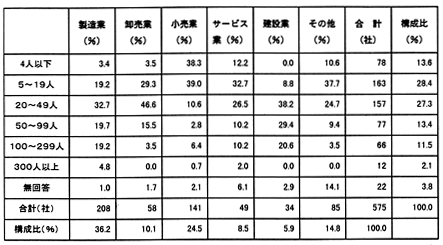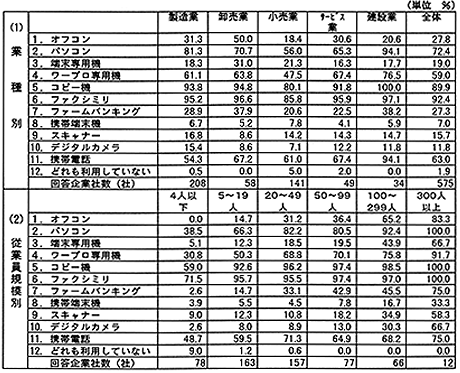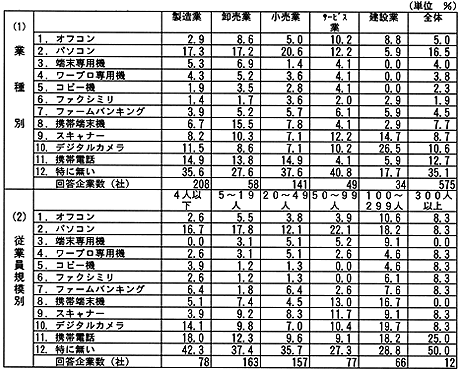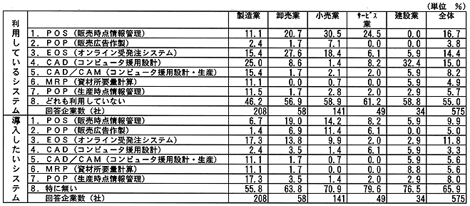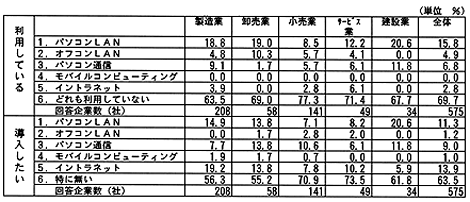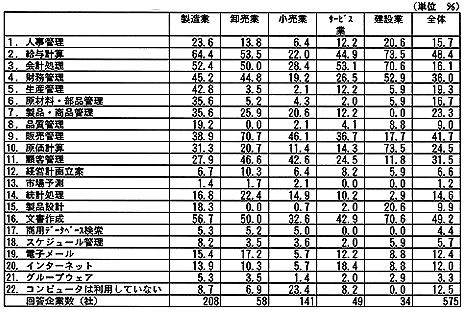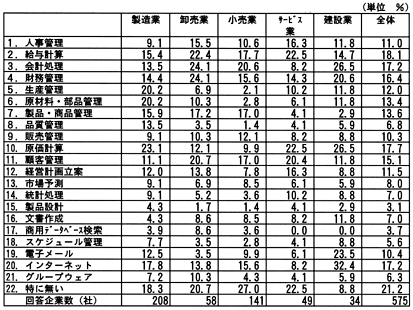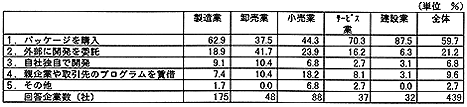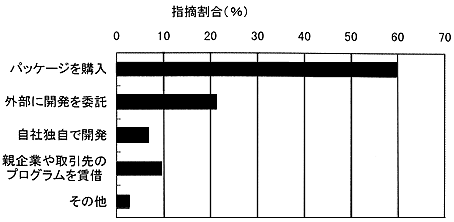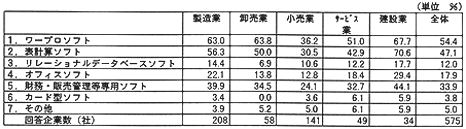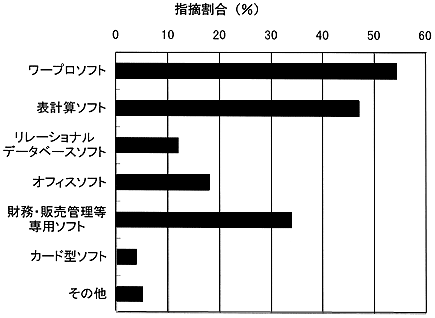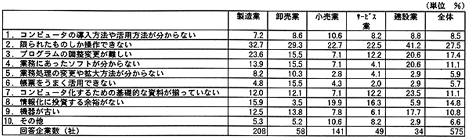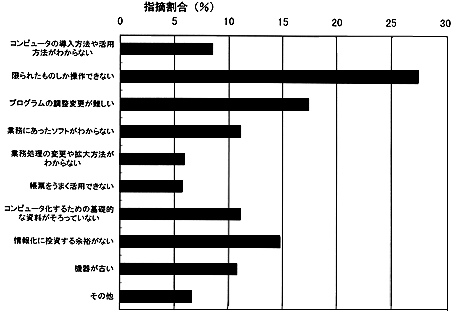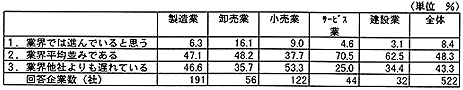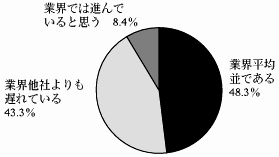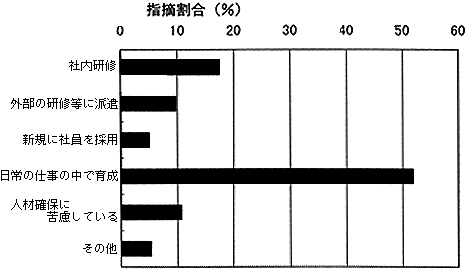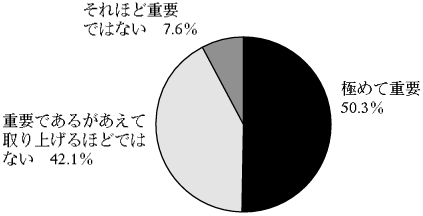|
1.調査方法
本調査は、県内企業の中から1,947社を無作為に抽出し、平成9年6月時点における情報機器の利用状況等を郵送による書面調査で実施した。このうち575社から有効な回答があり、回収率は29.5%であった。
2.回答企業の概要
集計は、表1のように回答企業を製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、その他の6業種と、従業員数の規模別に4人以下、5〜19人、20〜49人、50〜99人、100〜299人、300人以上の6種に分けて行った。
なお、その他の業種は表2以降の集計表には結果を掲載していないが、「全体」の結果には含まれている。
表1 回答企業の構成
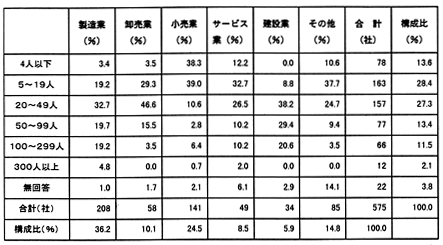
表2 現在利用している情報機器
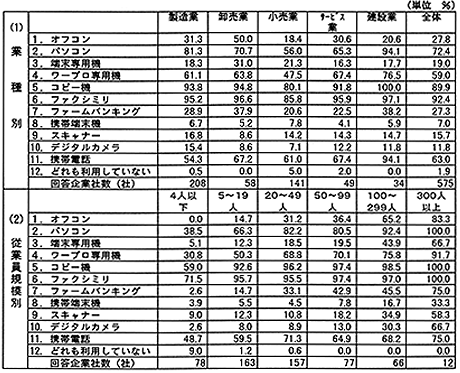
1.情報機器の利用状況
パソコン導入率は72.4%
現在一般に利用されている情報機器11種を取り上げて、調査時点におけるそれらの利用率を掲載したのが表2である。
11種の中で最も利用率が高かったのはファクシミリで、92.4%の企業が利用している。次いで、コピー89.9%、パソコン72.4%、携帯電話63.0%、ワープロ専用機59.0%となっている。また、回答のあった575社のうち、81.2%に当たる467社がオフコン、パソコン、端末専用機のいずれかのコンピュータを導入している。これは前回の調査結果(平成7年6月時点)に比べ、6.9ポイント上昇しており、県内企業の情報化は着実に進展している。特に、パソコンの導入率を見ると前回の65.1%から7.3ポイントも上昇しており、最近のパソコンブームが、全国同様に県内企業の情報化に大きく影響している事が分かる。
しかしながら、オフコンやパソコンの利用率を従業員数の規模別に見ると、規模が大きくなるに連れて利用率が着実に高く、企業規模による利用格差は依然として大きい。
今後導入したい情報機器を見たのが表3。回答企業全体では35.1%が「特に無い」としているが、16.5%がパソコンを指摘し、次いで携帯電話の12.7%となっている。
業種別では、小売業(20.6%)、製造業(17.3%)、卸売業(17.2%)でパソコンを導入したいとする企業が多いのに対して、建設業では5.9%しかなかった。
また、製造業・小売業(14.9%)では携帯電話、建設業(26.5%)ではデジタルカメラを導入したいとする企業が多くみられる。
近年のデジタルブームを追い風に、パソコンや移動体通信、デジタルカメラへの要求が、県内企業においても高くなってきているようである。
表3 今後導入したい機器
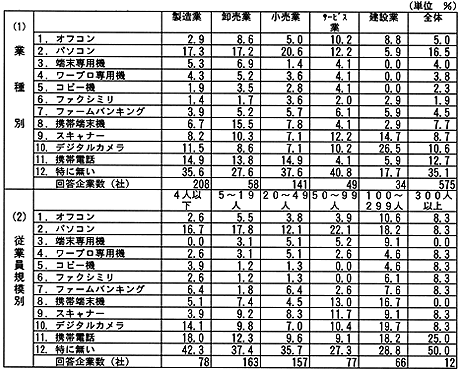
2.コンピュータシステムの利用状況
建設業の32.4%がCADを導入
コンピュータを利用した情報システムの利用状況を見たのが表4だが、業種により利用は大きく異なる。
業種別に利用率を見ると、製造業ではCADシステムを25.0%の企業が、卸売業ではEOSを27.6%が、小売業ではPOSシステムとEOSシステムをそれぞれ30.5%、18.4%の企業が利用している。また、サービス業ではPOSシステムを24.5%の企業が利用し、建設業ではCADシステムを32.4%の企業が利用している。これまで、建設業においては実行予算等の管理にコンピュータシステムを活用したいとする企業が多かったが、最近は、パソコンCAD等の低価格化により設計等の個別業務にコンピュータを活用したいとする企業が増えてきている。
一方、今後導入したいシステムとしては、製造業ではEOSシステム(17.3%)を導入したいとする企業が多い。また、卸売業、小売業、サービス業ではPOSシステムを導入したいとする企業が、それぞれ卸売業(19.0%)、小売業(14.2%)、サービス業(8.2%)と多くなっている。
表4 現在利用している・今後導入したいコンピュータシステム
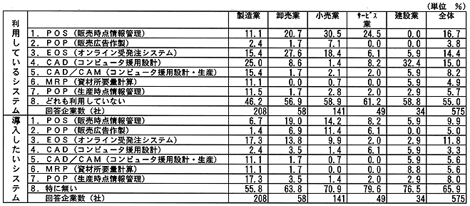
3.ネットワークの利用状況
遅れ目立つネットワーク利用
コンピュータを利用したネットワークの利用状況を見たのが表5。どの業種にも共通してパソコンLANとする企業が多かったものの、その利用率は全体で15.8%に留まっている。
またパソコン通信も6.8%と低く、コンピュータ単体の利用からネットワ−クとしての利用を考える企業が全国的に多くなっている中において、どれも利用していない企業が7割にも達し、情報ネットワークへの取り組みに遅れが目立つ。
しかし、今後利用したいネットワークとしては、イントラネットを13.9%が、次いでパソコンLANを11.3%の企業が指摘している。ネットワークの活用を前提としたビジネスが広がっている中で、社内情報の共有化や社外への情報発信に積極的にネットワークを取り組んでいこうという機運も見られる。
表5 現在利用している・今後利用したいネットワーク
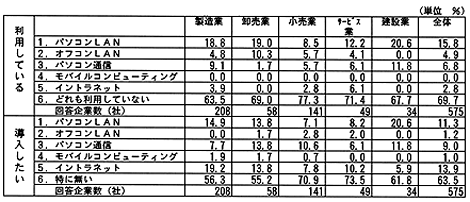
4.コンピュータ処理業務
今後は原価管理やインターネットに注目
現在コンピュータで処理している業務の内容を見たのが表6、また、今後コンピュータ化したい業務を見たのが表7である。
表6 現在コンピュータで処理している業務
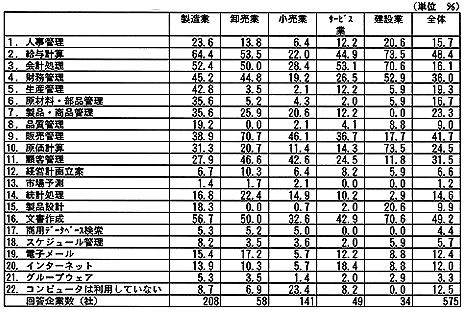
表7 今後コンピュータ処理をしたい業務
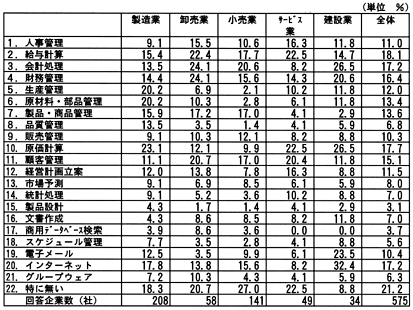
(共通して処理率が高い業務)
「各業種に共通してコンピュータ処理が進んでいる業務には、給与計算(48.4%)、文書作成(49.2%)、販売管理(41.7%)が挙げられ、いずれも4割以上の企業がコンピュータで処理している。また、最近話題になっているインターネットは、12.0%の企業が活用している。インターネットブームは一頃の勢いは見られなくなったものの、着実に浸透しており今後も利用率は高まるものと予測される。
これらに対して、経営計画立案や市場予測、グループウェア等の戦略的な活用はまだまだ低い。
今後処理したい業務としては、これらに加え原価計算(全体では17.7%)やインターネット(同17.2%)を指摘する企業が多い。
(製造業)
製造業では、42.8%の企業が生産管理をコンピュータにより処理している。今後処理したい業務としては原価計算(23.1%)や生産管理(20.2%)を指摘する企業が多く、この分野のコンピュータ化はいっそう進むものと考えられる。
(卸売業)
卸売業では、70.7%の企業が販売管理をコンピュータ化している。その反面、卸売業で重要な製品・商品管理については25.9%に留まっている。今後については、20.7%の企業が顧客管理を指摘しており、マーケティング活動や顧客の囲い込み等に役立てたいとする企業が多い。
(小売業)
小売業でも、46.1%が販売管理を42.6%が顧客管理をコンピュータで処理している。今後においては、17.0%の企業が製品・商品管理、顧客管理を指摘している。
(サービス業)
サービス業では、会計処理(53.1%)、給与計算(44.9%)に加え、販売管理(36.7%)と顧客管理(24.5%)をコンピュータ処理している企業が多い。
(建設業)
建設業では、原価計算をコンピュータで処理している企業が73.5%に達している。実行予算の管理や工事別の原価管理は、収益面で大きな影響を与えることからコンピュータ化を進める企業が多い。また、今後処理したい業務においては、インターネットと答えた企業が32.4%と最も多く、原価計算とする企業も26.5%に達している。
5.ソフトウェアの導入方法
パッケージが主流に
現在利用しているソフトウェアの導入方法について見たのが表8及び図1。全体で59.7%がパッケージプログラムを購入し利用しているとし、2番目の「外部に開発を委託」の21.2%を大きく上回っている。
特に建設業では9割近くがパッケージを利用している。その理由としては、パソコンの性能向上とともに質の高いパッケージソフトが提供されるようになったことが考えられる。今やパッケージソフトの活用がソフト調達の主流になりつつある。
表8 現在利用しているソフトウエアの導入方法
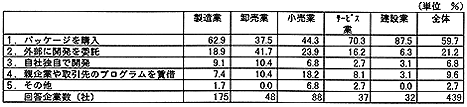
図1 ソフトウエアの導入方法
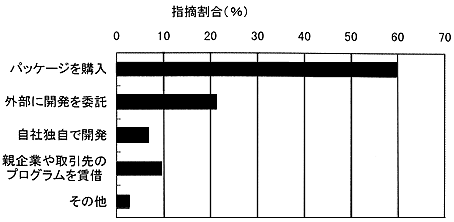
6. 現在利用しているパッケージソフト
2社に1社が表計算ソフトを利用
現在利用しているパッケージソフトをみたのが表9及び図2。ワープロソフト(54.4%)と表計算ソフト(47.1%)は、全体で過半数の企業が利用しているのに対して、リレーショナルデータベースソフト(12.0%)やカード型ソフト(3.8%)の浸透度は低い。これは、社内においてプログラムを組めるような人材が、まだまだ不足していることを物語る数値であろう。
表9 現在利用しているパッケージソフト
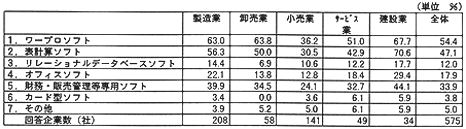
図2 現在利用しているパッケージソフト
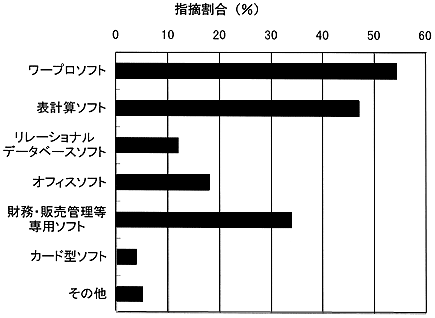
7. 情報化を進めていく上での課題
「誰もが操作できるように」が課題
情報化を進めていく上での課題を見たのが表10及び図3。「限られたものしか操作できない」が全体で27.5%と最も多く、中でも建設業では4割を超えている。次いで「プログラムの調整変更が難しい」(17.4%)、「情報化に投資する余裕がない」(14.8%)の順となっている。
社内での社員の意識・知識・技術の向上は、情報化を進めていく段階に応じて常にクリアすべき課題である。
表10 情報化を進めていく上での課題
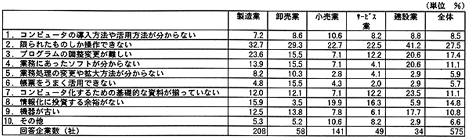
図3 情報化を進める上で、抱えている課題
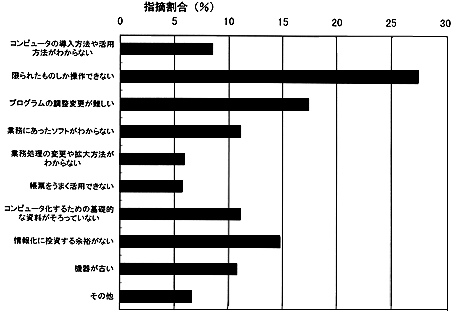
8. 自社の情報化レベル
4割以上がレベルの遅れを認識
自社の情報化レベルを見たのが表11及び図4。「業界では進んでいると思う」と答えた企業は全体で8.4%に留まり、「業界他社よりも遅れている」と答えた企業は43.3%となっている。業種別に見ると、サービス業では7割以上の企業が「業界では進んでいると思う」「業界平均並みである」と答えているが、逆に小売業では53.3%の企業が「業界他社よりも遅れている」と答えており、他の業種に比べ情報化への対応が遅れているという認識が強い。
表11 自社の情報化レベル
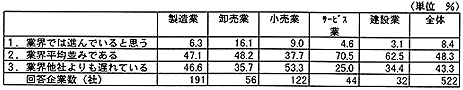
図4 自社の情報化レベル
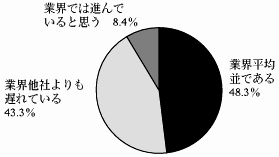
9. 情報化を担当する人材の確保
情報化は日常業務の中で育成
情報化を担当する人材を、どのようにして確保しているのかを見たのが図5。「日常の仕事の中で育成」が全体で51.9%と他を大きく上回り、次いで「社内研修」(17.4%)となっている。情報化には従来の社内の人材で対応し、日常業務の中で育成している企業がほとんどで、新規に社員を採用するのは5.0%にすぎなかった。しかしコンピュータ要員の必要性を感じ、「人材確保に苦慮している」企業も1割程度みられる。いずれにせよ、企業の経営・情報化には、人材育成が最も重要なポイントであり、情報化のカギとなっている。
図5 人材の確保
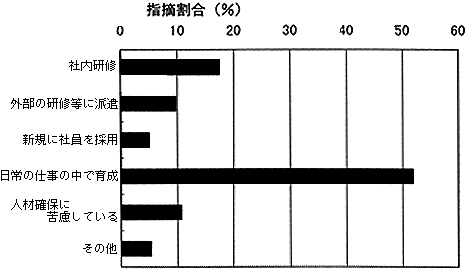
10. 情報化の捉え方
経営戦略上、情報化は不可欠
情報化の捉え方を見たのが図6。経営戦略上、情報化が「極めて重要である」と答えた企業は全体で50.3%で、「それほど重要ではない」とする企業は7.7%にすぎず、県内中小企業においても、情報化へのニーズは急速に高まっている。パソコン、オフコンが普及し、これからは情報機器を単に利用するだけではなく、いかに上手く活用するかということが一層重視され、この回答結果を見ても、「情報化」というものが企業にとっては、今まで以上に優先順位の高い経営課題になってきていることが分かる。
図6 情報化の捉え方
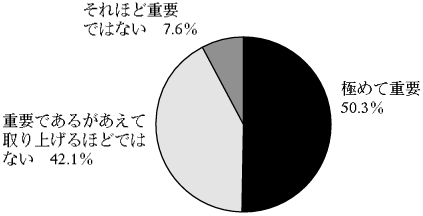
今や企業の規模や業種を問わず、経営にとって「情報化」への取り組みは避けては通れないものとなっています。県内中小企業における情報化は、現段階では給与計算・財務・会計や販売事務などでの経営の効率化が主たる狙いとなっており、社内LANやインターネット接続など、情報ネットワークへの取り組みにはまだまだ遅れが目立っているようです。さらには、情報化のためのコストや人材面で悩んでいる姿も浮き彫りになっています。当中小企業情報センターでは、今回の調査結果を業務に活かし、企業の情報化を支援していきたいと考えております。
最後になりましたが、本調査にご協力下さいました皆様に厚く御礼申し上げます。
|